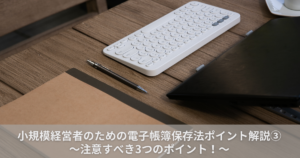中小企業の皆さまの中には下請法の適用業者の方も多くいらっしゃると思います。
下請法、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と呼ばれるこの法律は、1956年に制定され、主に中小企業や個人事業主を保護することを目的とした法律です。この法律は、親事業者と下請事業者との間に存在する経済的な力関係の不均衡を是正し、下請事業者が不当な扱いを受けることを防ぐために設けられました。下請法は、親事業者による下請代金の不当な減額や支払いの遅延、返品の強要などの行為を禁止し、取引の公正化を図ることを目的としています。
具体的には、下請法は、取引の内容や事業者の資本金に基づいて適用対象を定め、親事業者に対して義務や禁止事項を明確に規定しています。このように、下請法は独占禁止法を補完する形で、企業間の取引における公正性を確保し、経済の健全な発展を促進する重要な役割を果たしています。
近年では、下請法の適用範囲やその運用に関する議論が活発化しており、特に中小企業の経営者にとっては、法令遵守が求められる重要なテーマとなっています。そこで今回は、気になる方も多い、その「下請法」について少しお話をさせていただきたいと思います。
下請法の基礎知識
下請法の概要
下請法とは、日本における下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律です。この法律は、親事業者が下請事業者に対して不当な扱いを行うことを防ぐために制定されました。具体的には、親事業者が下請事業者に対して代金の支払いを遅延させたり、不当に減額したりする行為を禁止しています。
下請法の適用対象となる4つの取引
① 物品の製造委託
② 物品の修理委託
➂ 情報成果物の作成委託(プログラムの作成に限る)
④ 役務提供委託(運送や物品の保管など)
この法律は、親事業者の資本金規模に応じて適用される条件が異なります。例えば、親事業者の資本金が3億円を超える場合、資本金が3億円以下の事業者への委託が対象となります。また、親事業者には、下請事業者に対して書面を交付する義務や、支払期日を定める義務が課せられています。支払期日は、下請事業者が提供したサービスや商品を受領した日から起算して60日以内に設定しなければなりません。
違反があった場合、親事業者は公正取引委員会からの勧告や指導を受けることがあり、場合によっては企業名や違反内容が公表されることもあります。したがって、親事業者は下請法を遵守することが求められ、下請事業者も自らの権利を理解し、適切に行動することが重要です。下請法は、経済の健全な発展を促進するための重要な法律として位置づけられています。
下請法の目的
1.下請取引の公正化
下請法は、親事業者と下請事業者との間で行われる取引が公正に行われることを目的としており、親事業者がその優越的地位を利用して下請事業者に対して不当な要求をすることを防ぐために、様々な規制を設けています。これにより、下請事業者が不利益を被ることを防ぎ、取引の透明性を確保します。
2.下請事業者の利益保護
下請法は、資本力が小さい下請事業者の利益を保護するために設けられています。具体的には、親事業者による代金の不当な減額や支払いの遅延、返品などを禁止し、下請事業者が適正な対価を受け取れるようにすることを目指しています。これにより、中小企業や個人事業主が経済的に安定した運営を行えるよう支援しています。
この法律は、独占禁止法の補完的な役割を果たし、特に下請事業者が親事業者に対して声を上げにくい状況を考慮して、迅速かつ効果的に不当な取引を規制することを目的としています。
下請法の適用対象
下請法の適用対象は、主に取引の内容と当事者の資本金規模に基づいて定義されています。以下は、その詳細になります。
1.適用対象の取引
下請法が適用される取引は、以下の4つです。
① 製造委託 ⇒ 物品の製造を他の事業者に委託する場合。
② 修理委託 ⇒ 物品の修理を他の事業者に委託する場合。
③ 情報成果物作成委託 ⇒ プログラムの作成など、情報成果物を他の事業者に委託する場合。
④ 役務提供委託 ⇒ 運送や物品の保管、情報処理などのサービスを他の事業者に委託する場合。
2.資本金要件
下請法の適用には、親事業者と下請事業者の資本金規模が重要な要素となります。具体的には以下のような条件があります。
① 親事業者 ⇒ 資本金が5,000万円を超える法人。
② 下請事業者 ⇒ 資本金が5,000万円以下の法人または個人。
このように、親事業者が資本力のある企業であり、下請事業者がそれに対して資本力が小さい場合に、下請法が適用されます。
下請法は、親事業者と下請事業者の間での不公正な取引を防ぐために設けられた法律であり、特に中小企業や個人事業主を保護する役割を果たしています。適用対象となる取引の内容と資本金の規模が明確に定義されているため、関係者はこれらの条件を理解し遵守することが重要です。
下請法における親事業者の義務と禁止事項
下請法において、親事業者には特定の義務と禁止事項が定められています。これらは下請事業者の利益を保護し、公正な取引を促進するためにとても重要になってきます。
親事業者の義務
親事業者には以下の4つの主要な義務があります。
1.書面の交付義務
親事業者は、下請事業者に対して発注内容を記載した書面(3条書面)を直ちに交付する義務があります。この書面には、発注者と下請事業者の名称、発注日、納期、下請代金の額、支払期日などが含まれなければなりません。
2.支払期日を定める義務
下請代金の支払期日は、物品等を受領した日から60日以内に定める必要があります。できる限り短い期間で設定することが求められます。
3.書類の作成・保存義務
親事業者は、下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります。この書類には、給付内容や下請代金の額、支払日などが記載されます。
4.遅延利息の支払義務
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は遅延利息を支払う義務があります。この利息は、未払い金額に年率14.6%を乗じた額となります。
親事業者の禁止事項
親事業者には以下の11の禁止事項が定められています。
1.受領拒否の禁止
下請事業者が納入した物品等の受領を不当に拒むことは禁止されています。
2.下請代金の支払遅延の禁止
定められた支払期日までに下請代金を支払わないことは禁止されています。
3.下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決定した下請代金を減額することは禁止されています。
4.返品の禁止
下請事業者に責任がない場合に、受領後に物品を返品することは禁止されています。
5.買いたたきの禁止
通常の対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることは禁止されています。
6.購入・利用強制の禁止
親事業者が指定する物品や役務を強制的に購入または利用させることは禁止されています。
7.報復措置の禁止
下請事業者が不当な行為を報告したことを理由に、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償で支給した原材料等の対価を、支払期日より早く支払わせることは禁止されています。
9.割引困難な手形の交付禁止
一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することは禁止されています。
10.不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請事業者から金銭やサービスを不当に提供させることは禁止されています。
11. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付内容を変更させたり、やり直しをさせることは禁止されています。
これらの義務と禁止事項は、下請事業者の権利を保護し、公正な取引環境を維持するために重要です。親事業者はこれらを遵守することで、法的なトラブルを避けることができます。
下請法の罰則規定
下請法には、親事業者が遵守すべき義務や禁止行為に対する罰則規定が設けられています。これらの規定は、下請事業者の権利を保護し、公正な取引を促進するために重要です。
罰則の概要
1.罰金の科せられるケース
親事業者が下請法に定められた義務を怠った場合、最大で50万円の罰金が科せられる可能性があります。具体的には以下のような場合です:
- 注書面の交付義務を怠った場合(下請法第3条)。
- 書類の作成・保存義務を怠った場合(下請法第5条)。
- 公正取引委員会や中小企業庁の調査に対して虚偽の報告をした場合や、報告をしなかった場合(下請法第11条、第12条)。
- 立入検査を拒否または妨害した場合。
2.違反行為の具体例
下請法に違反する行為として、以下の11項目が定められています。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 不当な返品
- 買いたたき
- 購入
- 利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
3.社会的信用の低下:
下請法に違反した場合、勧告や指導が行われ、その内容が公表されることがあります。この公表により、企業の社会的信用が低下し、今後の取引に影響を及ぼす可能性があります。
4.改善措置の要求:
違反が認められた場合、親事業者は改善対応を行い、その結果を報告する必要があります。場合によっては、下請事業者に対して不利益の原状回復を求められることもあります。
これらの罰則規定は、親事業者が下請事業者に対して不当な取引を行わないようにするための重要な枠組みを提供しています。親事業者は、下請法を遵守することで、法的なトラブルを避け、健全な取引関係を維持することが求められます。
下請法の適用対象となる業種、ならない業種

下請法は、親事業者と下請事業者の取引における公正性を保ち、下請事業者の利益を守るための法律です。この法律の適用対象となる具体的な業種は、以下のように分類されます。
下請法の適用対象となる業種
1.製造業
製造委託: 物品の製造を外部の事業者に委託する場合。例えば、自動車メーカーが部品の製造を外注するケースなどが該当します。
〈具体例〉
自動車、電子機器、食品加工など。
2.修理業
修理委託: 物品の修理を外部に委託する場合。例えば、家電メーカーが製品の修理を専門の修理業者に依頼することが含まれます。
〈具体例〉
家電修理、自動車整備、機械修理など。
3.情報成果物作成業
情報成果物作成委託: ソフトウェアやプログラムの作成を外部に委託する場合。例えば、ソフトウェア開発会社が特定の機能を他の開発会社に依頼することが該当します。
〈具体例〉
ソフトウェア開発、デザイン制作、映像制作など。
4.サービス業
役務提供委託: サービスの提供を外部に委託する場合。例えば、運送業者が一部の運送業務を他の運送会社に委託することが含まれます。
〈具体例〉
運送業、清掃業、コールセンター業務など。
これらの業種は、下請法の適用を受けることで、親事業者からの不当な扱いを防ぎ、取引の公正性を確保することが目的とされています。また、下請法は、親事業者の資本金や取引内容に基づいて適用されるため、具体的な取引の内容や関係性が重要です。
下請法の適用対象とならない業種
1.建設業
下請法は、建設業における取引には適用されません。建設工事は、建設業法に基づいて別途規定されているため、下請法の適用外となります。
2.市販品の売買
市販品の売買に関する取引も下請法の適用対象外です。これは、親事業者が規格や品質を指定して依頼する取引ではないためです。
3.自社内での業務
自社で用いる情報成果物を自社内で作成する場合や、発注者自身のために行う役務提供も下請法の適用外となります。具体的には、発注者が自社の業務の一環として行うサービスの提供は対象外です。
下請法は、主に中小企業を保護するための法律ですが、建設業や市販品の売買、自社内での業務などはその適用対象外となります。これにより、特定の業種や取引においては、下請法の規制を受けないことになります。
建設業が下請法の適用にならない理由
1. 法律の適用範囲の違い
〈建設業法の優先適用〉
建設業における下請け取引は、主に「建設業法」に基づいて規制されています。下請法は、製造業やサービス業などの取引に適用される法律であり、建設工事に関しては建設業法が適用されるため、下請法の適用はありません。
〈取引内容の特異性〉
下請法は、製造委託や修理委託、情報成果物の作成委託など、建設工事以外の取引に適用されます。建設工事は、建設業法によって規制されており、これにより建設業者間の取引は下請法の対象外となります。
2. 規制の目的の違い
〈下請法の目的〉
下請法は、下請事業者の利益を保護し、親事業者による優越的地位の濫用を防ぐことを目的としています。一方、建設業法は、建設工事に関する契約の適正化や、工事の品質確保を目的としています。このため、両者の法律は異なる目的を持っており、適用される範囲も異なります。
3. 具体的な取引の性質
〈建設工事の特性〉
建設工事は、プロジェクトごとに異なる要件や条件が存在し、契約内容も多岐にわたります。これに対して、下請法はより一般的な取引に適用されるため、建設業の特性に合致しない部分があります。
以上の理由から、建設業は下請法の適用外とされ、代わりに建設業法が適用されることになります。建設業者は、下請法の規制を受けることなく、建設業法に基づいて取引を行う必要があります。これにより、建設業界特有の取引の透明性や公正性が確保されています。
最後に

繰り返しにはなりますが、下請法とは、日本における下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律です。この法律は1956年に制定され、親事業者と下請事業者との間に存在する経済的な力関係の不均衡を是正するために設けられました。
下請法は、親事業者が下請事業者に対して不当な減額や支払いの遅延、返品の強要などを行うことを禁止し、取引の公正性を確保することを目指しています。具体的には、下請法は親事業者に対して書面の交付義務や取引記録の保存義務を課し、違反した場合には罰金が科されることがあります。また、下請法の適用対象となる取引は、物品の製造や修理、情報成果物の作成、役務の提供など多岐にわたります。
近年では、経済情勢の変化や新型コロナウイルスの影響により、下請事業者の立場がさらに厳しくなっているため、下請法の重要性が増しています。したがって、親事業者はこの法律を正しく理解し、遵守することが求められています。
下請法は、企業間の取引における公正性を確保し、経済の健全な発展を促進するための重要な枠組みとなっています。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4881dbee.71b547e5.4881dbef.97aedbac/?me_id=1319439&item_id=10003315&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcicib%2Fcabinet%2F11786369%2F11793338%2F11949320%2F3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)